第8報でお解かりして頂けたと思いますが、全身の細胞に中性脂肪やコレステロールを供給しているリポタンパク質の代謝システムは非常に優れており人工では作れません。しかし人類がこんなに長寿になることを想定したシステムではなかったので、ほころびが出てきました。その1つが、第3報で述べたアポB100の服が汚れた(=酸化された)場合の処理方法です。酸化されたアポB100は遺物を捕らえる白血球の1種の ”マクロファージ’” を利用して処理いますが、このアポBの酸化が増え続けるため処理し切れずドントン溜まります。これが動脈硬化や心筋梗塞が起こる原因です。
話しを少し戻して、VLDL粒子やLDL粒子を細胞内に取り込むには、その粒子の受容体が必要です(受容体 : レセプター: レセプターの発見=ノーベル賞受賞技術)。
すなわち受容体(レセプター)とはリポ蛋白質を細胞へ取り込むための玄関口の鍵穴と思ってください。
当然鍵であるLDL粒子のアポBのC末端が酸化した(汚れた)場合、玄関は開きませんね。この酸化したVLDL粒子やLDL粒子は侵入した細菌のようなものですから白血球の1種であるマクロファージで素早く回収除去(貪食)されますが、酸化されたVLDLやLDLが多くなり過ぎると動脈壁の内膜に蓄積し粥状動硬化を引き起こします。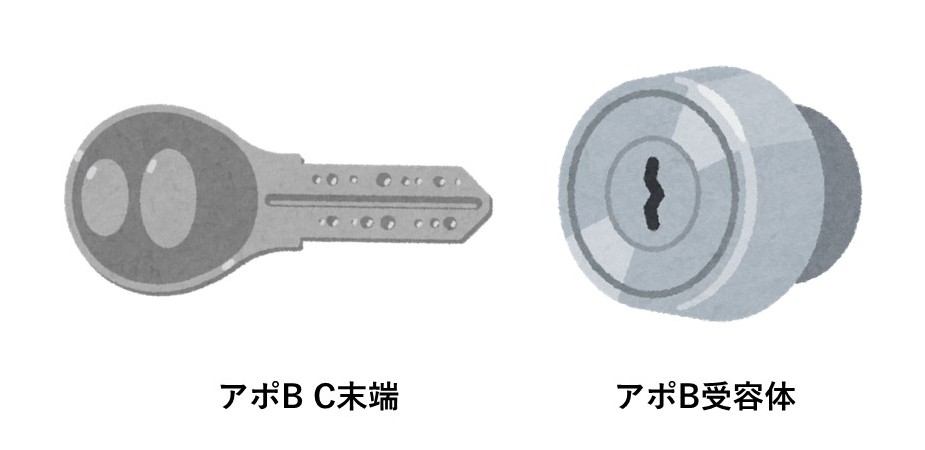
【鍵と鍵穴の図】
第6報で述べた易酸化VLDLと易酸化LDLとは、第8報で説明したリポタンパクリパーゼ(LPL)に接触し、VLDLとLDLの中性脂肪の一部か水解しアポBのC末端が露出したままの状態をいいます。アポBのC末端が露出したまま血液中を循環していると活性酸素でアポBのC末端が簡単に酸化されます。
この酸化したVLDLやLDL)は素早くマクロファージに貪食されるので血中には存在しないと言われています。
我々は酸化されやすい(易酸化)VLDLやLDLを検出する方法を第7報で紹介した特許で公開しました。易酸化VLDLやLDLを持っている人を見つけることができれば心筋梗塞は発症前に治療することが出来ます。そのため患者から採血後血清にした検体を2つに分けその1方を37℃2時間インキュベーションします。そしてインキュベーション前後の検体のリポタンパク質の変化を電気泳動法などで調べ比較すればば易酸化VLDLやLDLの存在を簡単に見つけことができます。
この事実は一度心筋梗塞になった患者が手術後適切な治療により再発を防げていることで証明されています。
以上、採血後のリポタンパク質を37℃2時間インキュベーションした前後のリポタンパク質を電気泳動法でつぶさに調べれば、酸化されやすい(易酸化)VLDLやLDLを持っている患者を見つけることができることを発見し特許(特許第6454950号)を取得しました。
第9報 課題に対する結論
採血後の血清を37℃2時間インキュベーションすると、採血時に存在するリポタンパク質リパーゼ(LPL)を持っている人と持っていない人を区別することができる。
「 リポタンパク質リパーゼ(LPL)は、細胞膜結合型酵素であるが、何らかの理由で受容体にたどり着けなかった場合、血中に漏れ出て酸化VLDLやLDL粒子を作る事がある。」

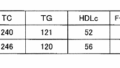
【記事一覧】
第1報 動脈硬化の発生原因が解明されました
第2報 LDL粒子とは何者か?
第3報 何故LDL粒子は酸化されるのでしょうか?(No.1)
第4報 なぜLDL粒子は酸化されるのか? (No.2)
第5報 なぜLDL粒子は酸化されるのか? (No.3)
第6報 第5報で述べた「易酸化LDL」の有無をあらかじめ日常検査で調べることができます
第7報 「易酸化LDL」の特許広報
第8報 「LDL粒子生成の秘密」
第9報 課題「検体を37℃2時間インキュベーションしただけで何故 易酸化LDL存在が解るのですか?」
第10報 易酸化LDLの測定
第11報 リポタンパク質の測定法
第12報 ポリアクリルアミドゲルディスク電気泳動(PAGE)法による健常者の濃度図
第13報 脂質異常症(高脂血症)のWHO型の判定(Classification)
第14報 脂質異常症の改変WHO型判定法のアルゴリズム
第15報 脂質異常症のWHO型判定結果の読み方
第16報 動脈硬化の発生原因が解明されました No.2